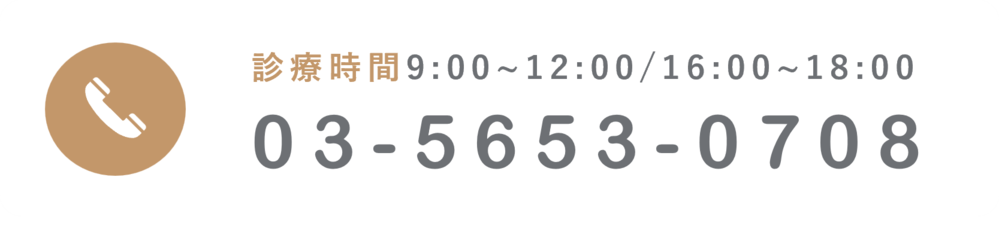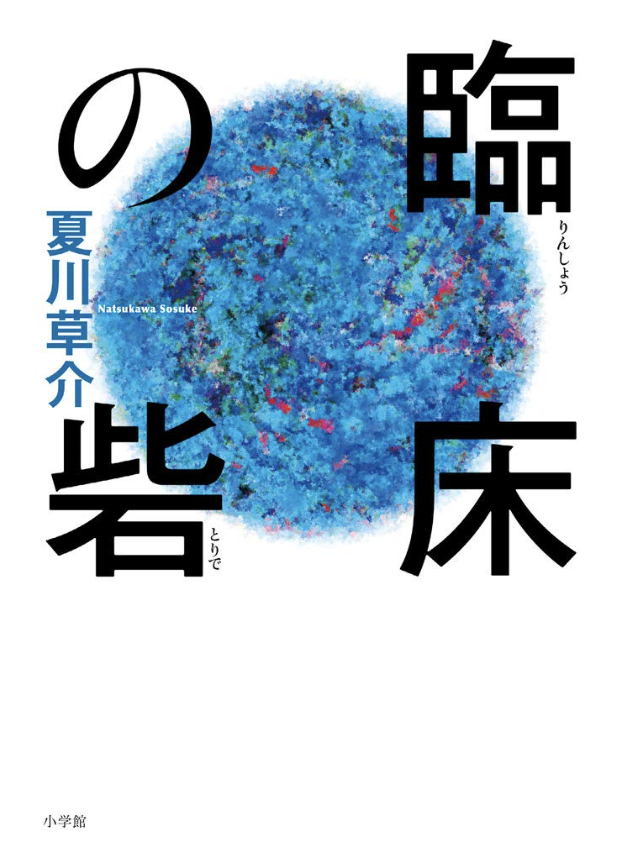
暑いです。東京オリンピックが盛り上がる一方で、都内の感染者数も相変わらずの増加です。
都内の50歳台のコロナの患者さんが呼吸が苦しくなったとのことで救急車を呼んだところ、100カ所の医療機関に断られ8時間後に50キロ離れた病院に入院できたというニュースを見ました。
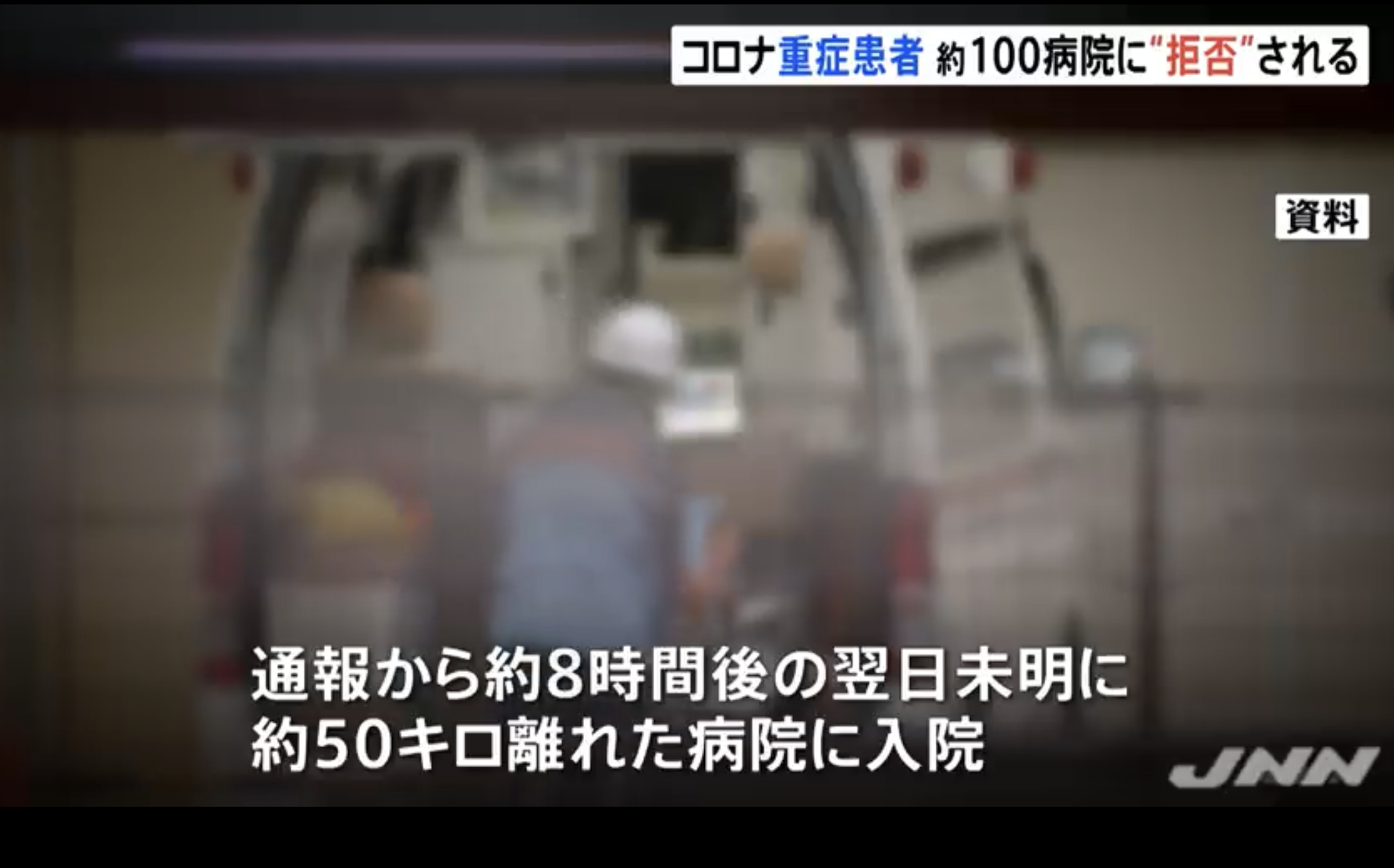
断った100の医療機関について、何とかすこし頑張れば1人ぐらい入院させられたのではと、一般の方は思うかもしれませんが、現場ではもはやそれも無理なのでしょう。
以前慈恵医大の分院で仕事をしていたとき、具合の悪い患者さんの転院先をみつけるのにやはり10時間ぐらいいろんな病院に夜通し電話を掛けたのを思い出しました。
多くの病院が既に飽和状態になってきたのではと心配してしまいます。
「臨床の砦」(夏川草介著)はまさにコロナを受け入れる立場にある病院の物語です。
長野県の病院でコロナ診療にあたっていた内科の先生が、今年の第3波をどう乗り切ったか、をリアルに描いています。
200人規模の中規模の病院という砦を使命感と献身的な戦いで護った「戦記」のようなものです。
思わず、何回も「分かる、分かる」とか「そうだよなー」と引き込まれて一気に読んでしまいました。
以下一部抜粋。
ーー医師の精神はそろそろ限界に近くなっている。
敷島は、そっと手元に視線を落とした。
虫垂炎の診断が二時間待ち。
肺炎患者は自宅で入院待機。
近隣の医療機関はいまだ準備が整わず、明らかに対応に遅れがある。
院内を顧みれば、コロナにかかわる医師も看護師もまともな休息が取れていない。
この状況で、今日もこの小さな病院に大量の患者が押し寄せてくる。
すでに一年近くの長期にわたる消耗戦で確実に疲弊しているところに、過去に例のない圧倒的な大軍が迫っているということだ。
敷島は、頭の中でひとつずつ問題点を数えあげ、やがて小さく嘆息した。
「この戦、負けますね・・・・」
ドキュメンタリーではないものの、小説だからこそ、1人の人間として医師たちが自分の家族も抱えながら、苦悩しながら必死で奮闘しているのが伝わってきます。
医療現場と、国、自治体、マスコミ、市民それぞれの温度差もよく描かれ、そんな中コロナ患者が家族に看取られることもなく孤独で悲惨な最後を遂げていく様子もリアルです。
現在、病床が逼迫してくるなか、本気で責任をもって最善策をとれるリーダーが改めて必要だと感じさせてくれる本でもありました。
日本はコロナに打ち勝てるのでしょうか?


 ホーム
ホーム 医院紹介
医院紹介 診療案内
診療案内 当院の特徴
当院の特徴 初めての方
初めての方